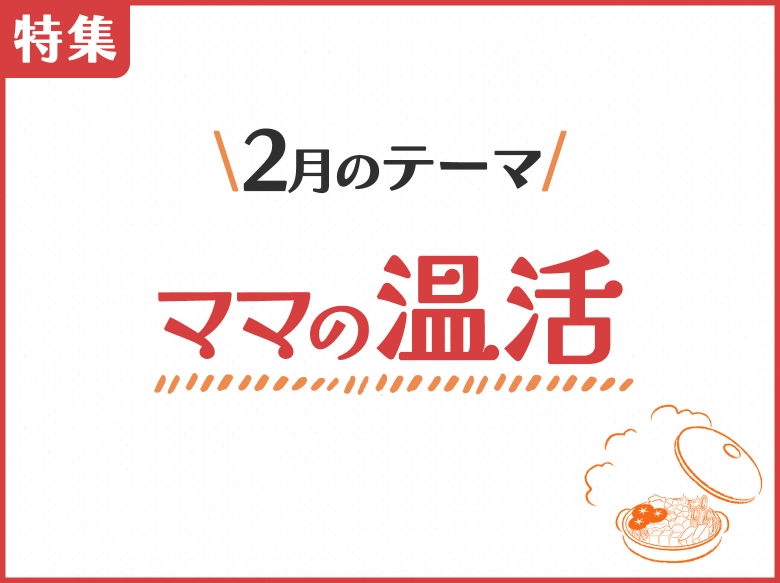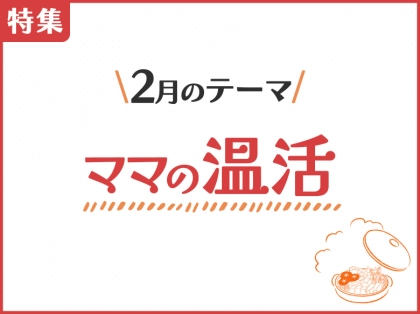画像/筆者提供
Lifestyle
【医師監修・執筆連載①】「また怒っちゃった…」をなくしたい!『イライラとの付き合い方』発達専門の小児科医ママに学ぶ
「今日こそ怒らないように気をつけよう」 そう思って一日を始めても、気がつけば大きな声を出してしまっていた。 そんな経験、ありませんか? 特に子育てや家事、仕事そして自分のことも大切にしたい!と考えながら毎日マルチタスクをこなすママは、「しつけ」も精一杯工夫したいところ。けれど、きょうだいがいる場合、年齢に応じた対応の違いや叱り方に戸惑うことは当たり前です。そんなママたちの悩みを同じように経験してきた私が体験談を交えつつ、専門医の知見と子育て研究家としての様々な角度から、イライラとの付き合い方、そして効果的な叱り方について、2回に分けてご紹介します。
西村佑美
小児科専門医、子どものこころ専門医
/一般社団法人 日本小児発達子育て支援協会 代表理事/3児ママ
大学病院で発達診療を学ぶ。発達特性に合わせた子育て経験を活かしママ友ドクター®活動や「子ども発達相談アカデミー VARY」を展開。著者「発達特性に悩んだらはじめに読む本」(Gakken)
https://lit.link/doctornishimurayumi
「怒ってばかり」のモヤモヤ、あなただけじゃありません
「朝から怒ってばかり…」 「こんな叱り方でいいのかな…」 「また感情的になってしまった…」 子育て中のママなら、誰もが経験するこんな思い。特に2歳以降の幼児期は、子どもの行動範囲が広がり、好奇心旺盛な反面、危険な行動も増える時期です。しかも口ごたえまでするようになってきた大きいお子さんがいる場合は、宿題や習い事など、新たな課題も加わってきます。例えば、こんな場面、心当たりはありませんか?
朝の支度中、まだパジャマを着たままの上の子に「早く着替えて!」と何度も声をかけているのに、一向に動き出す気配がない。その横で下の子が食パンを床に落とし始めた。思わず「もう!何度言ったらわかるの!」と声が大きくなってしまう。
あるいは、つい言うことを聞かない子どもに対し、「そんな子はもう我が家には必要ない」とか「鬼が来るよ!」「サンタさん来なくなるよ!」など脅すような言い方をしてしまう。ママ自身の焦りや疲れ、寝不足なども重なって、気がつけば感情が抑えきれないで声を荒げてしまう…。などなど。

「怒る」と「叱る」の違いを理解するところから始めよう
実は、多くのママが怒り方や叱り方に悩む背景には、「怒る」と「叱る」の違いが曖昧になっていることが関係しています。しつけなくては!という焦りから、この2つを混同していませんか?
「怒る」は感情の動き。誰にでも自然に湧き起こる感情ですが、「怒る」とはそれを相手にぶつけることと捉えてください。実は自分のネガティブをさらに増幅させ、心に沸き上がった不快感、ストレスを発散させるためのものなのです。
一方、「叱る」は、相手のことを思い、その成長を願って行う教育的あるいは指導的な行為。子どもに「こうすると危ないよ」「こうするとみんなが困る」「ママはこうしてほしい」などといった形で伝え、より良い行動を促すための声かけです。「しつけ」は「上手に叱る」ことが求められますね。
この2つの違いを自分なりに解釈して捉えられるようになると、「もう!何度言ったらわかるの!」という叫び声は、実は子どものためではなく、自分のイライラを発散させているだけかもしれないと、気づくことができます。客観的に自分を観察できるようになると、自然と冷静な声がけが増えていきますよ。
イライラと上手に付き合うために
感情的になりそうなとき、すなわち怒りそうになった時、私たちはどうすれば良いのでしょうか?
まずは、怒りの感情自体は自然なものだと受け入れることから始めましょう。「怒りたくなる自分」や「怒っている自分」を否定しなくて大丈夫です。大切なのは、その感情とどう付き合い、どう表現するか。ひとつのヒントに「アンガーマネジメント」という考え方があるのでご紹介します。
6秒ルールを味方につける
怒りが込み上げてきたとき、まず6秒待ってみましょう。たった6秒でいいんです。この時間があれば、感情的な状態から、理性的に考えられる状態に切り替わってきます。ゆっくりカウントするでもよし、何か呪文とか一発ギャグを唱えてみるのもよし。マイルールを決めておくといいですよ。
例えば、こんな場面を想定してみてください。
場面① スーパーでお菓子を買って!と駄々をこねられたとき
「あ、ここで「だめだよ!」と言ったら泣き叫ぶパターンだわ…」と予測できるのにイライラしてきたら 、息を大きく吸って6秒分の呪文を唱える
→→落ち着いて「お買い物リストにないものは買わないルールだったね」と冷静に伝える。伝えても上手くいかずに泣き叫びだすと、どんな説得もなかなか通用しないのが子ども。それでも、怒らずに対応できたママ自身をほめてあげて。そこからさらに「ルールを守ることを教えるのも親の役目」と割り切り対応しましょう。ちょっと大変ですがその場をいったん離れて冷静にさせてから戻るか、知らぬ顔で買い物を済ませてさっと連れて帰りましょう。この時「泣いちゃったけど、おかし我慢できたね、ルールを守れたねさすがだね!」と褒めてあげてくださいネ!
場面② きょうだい喧嘩が始まったとき
「また始まった!」とイラッとしたら、「いいかげんにしなさい!」と怒鳴りそうになる前に、その場を離れて6秒カウントするする。
→→きょうだい喧嘩の際は、親はレフリーのように冷静に介入するほうが上手くいくとされているので、冷静に状況を観察しイエローカードを出しつつ喧嘩が進むのを審判になったつもりで見てあげてください。案外、子どもたちのやり取りを通じて面白い発見がありますよ。
ちなみに私は、イライラして怒りたくなる状況では、早口で実況中継して6秒過ぎるのを待ちます。「おお、○○くんの肘が当たってコップが倒れて牛乳が机の上から下にぽたぽたと落ちていますね、大変だ、誰かが早く拭かないとあとで臭いが大変なことになってしまいます!」みたいに。

「怒る」という行為を見つめ直す
「怒る」という行為について、さらに1つ大切なことがあるので、お伝えしておきます。
実は、これまで「しつけのため」として容認されがちだった「怒る」行為の一部、特に体罰を伴うものが、法律で禁止されているのをご存知でしょうか?2020年4月1日から、日本では改正された児童福祉法および児童虐待防止法が施行され、親による体罰が法律で禁止されています。具体的には、以下のような行為は、昔なら「子を怒る」一連の流れだったかもしれませんが、現在では体罰の例として挙げられていて禁止されています。
●反省のために長時間正座させる
●友達を殴ったので、同じように子どもを殴る
●宿題をしないので夕飯を抜く
●ふざけるので頭をげんこつで叩く
●しつけとしてお尻を叩く
●大声で家族に暴言を吐く
●子どもの前で配偶者を殴る
「私が子どもの頃は、こうやって育てられた」という経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。でも、研究によって、体罰や暴言には以下のような影響があることが明らかになっています。
●攻撃的な行動を学習し、他者への暴力が増える
●自尊心が低下し、自己肯定感が育たない
●問題解決能力が身につかず、感情コントロールが難しくなる
特に深刻なのは、この影響が世代を超えて連鎖していく可能性があることです。なぜなら、私たち親は自分が受けた子育てしか知らないので、「自分もそうやって育てられたから効果がある、しつけは厳しくすべきだ!」という考えを持ってしまいがち。ここでストップさせることが大切なんです。覚えておいてくださいね!

イライラとの付き合い方、効果的な叱り方についてご紹介してきました。少しずつ意識して取り組んでみてください。次回の記事でも叱り方について触れながら「子どもの行動についての理解を深めていく」です。ぜひ読んでみてください。
構成・文/西村佑美(小児科専門医、子どものこころ専門医)
あわせて読みたい

Lifestyle
2024.12.15
「子どもの思考パターンを探ると、子育てはもっと面白くなる」ママ友ドクター®・ゆみ先生インタビュー(前編)
Recommend
[ おすすめ記事 ]

Lifestyle
まるで旅した気分♡セブンが仕掛ける【イタリアンカフェ】が本格的! 森由紀子

Lifestyle
「余ったお餅も秒でなくなる!」絶品リメイクレシピ♡材料2つで簡単にできるサクもちドーナツの作り方 rin

Lifestyle
【子連れカフェ】これがあれば無敵☆授乳室・おむつ台・キッズスペースがあるカフェ『UPCOFFEE』(埼玉県) peggy

Lifestyle
「無印良品でおうち時間がもっと好きになる♡」人気YouTuber厳選のおすすめアイテム全17選|第1弾 sena

Lifestyle
「気持ち良さすぎ~」なモフモフ寝姿に思わず歓喜♪ mamagirl WEB編集部

Lifestyle
「参上!我ら紅葉仮面!」自然のお面がかわいすぎるワンコたち♡ mamagirlWEB編集部
Check it out!