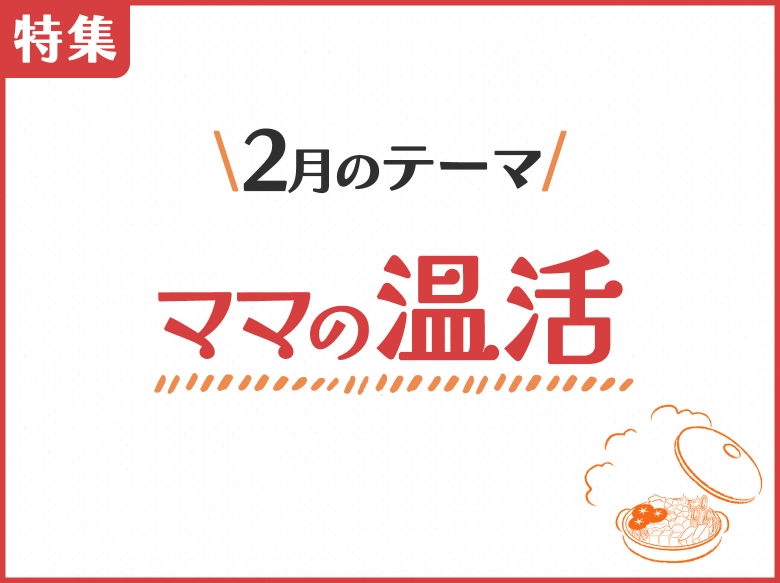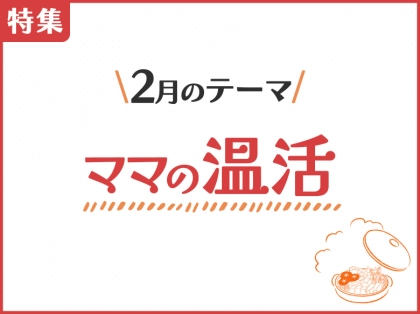出典:photoAC
Lifestyle
【門松の正しい飾り方!】置く場所やいつからいつまで飾るか、アパート・マンションでの飾り方も
お正月のシンボルのひとつでもある門松。正しい飾り方はご存じでしょうか。門松を飾るのは年に一度のことなので、じつはあまり知らない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、設置場所からなぜお正月に門松を飾るのか、門松の起源や飾る期間などを詳しく見ていきましょう。飾った後はどのような処分方法があるかもご紹介するので、お正月を迎える前にチェックしてくださいね。
■まずは基本から!お正月に門松を飾る意味を知ろう

初めに、お正月に門松を飾る意味や門松の種類について確認しましょう。
・お正月に門松を飾るのはなぜ?大きさで財力を示していた時期も
そもそもお正月とは「年神様を家へお迎えする」ための行事です。その年神様への目印として飾るのが、門松です。“わが家はここです”と示しているんですね。
古来から松には神様が宿るとも考えられていて、門松に使う松は、昔はその年の年神様が訪れる方角である恵方の山からとってきていました。そして、時代とともにサイズが大きくなったそうです。これは、大きさによって財力を示したい、よりご利益を授かりたいという思いの表れだといわれています。
ちなみに門松同様にお正月に飾る鏡餅は、招いた年神様に座っていただく座布団の意味合いがあり、しめ縄飾りは神聖な場所を示しているそうです。
・門松の形の意味と地域による形の違いは?

自分の家の門松と他の門松を比べると、形の違いに気づくこともあります。これは、門松にもさまざまな種類があり、地域差もあるからなんですよ。
一般的な門松の種類は「そぎ」「寸胴」の2種類。そぎは、松の中央にあしらわれた竹の上部が斜めに削がれています。切り口が笑った口に見えることから、縁起が良いとされています。一方、寸胴は切り口が水平で、口が開いていないためお金が逃げないと考えられているそう。銀行などお金を扱う場所で好んで飾られているのを見かけるかもしれませんね。
また、関東と関西といった地域によっても門松が異なります。関東では3本の竹の周りに短い松を置き、下を藁(わら)で巻きます。関西ではこの藁が竹になるケースが多いようです。
・門松に使われる竹の長さは3本とも違う!本体サイズの意味は

門松に使われる竹の長さは、1本だけ長くて残りの2本は同じ長さだと思っていませんか?じつは3本とも異なる長さで、7:5:3の比率になっているんだそう。2で割り切れない縁起物の比率となっています。
門松本体の大きさは、昔は財力を示すなどと考えられることもありました。大きな門松は6尺(180cm)ほどで、価格は一対で80,000円前後。小さなサイズでもご利益があるため、大きさや値段は心配しなくても大丈夫ですよ♡
■起源はいつ?歴史をさかのぼって門松の由来を知ろう

門松の起源は1000年以上前までさかのぼり、平安時代の「小松引き」が元だといわれています。小松引きとはその年の初めの子(ね)の日に外出し、長寿祈願のために小さな松の木を引き抜いてくるもの。当初は松だけを飾っていましたが、室町時代に入ると長寿を表す竹もあわせて飾られるようになりました。
■門松はいつからいつまで飾る?避けるべき日は

・松の内に飾る
「松の内」という言葉を聞いたことがあると思います。これは、お正月飾りを飾る期間のことです。関東と関西で期間が異なり、関東が12月13日~1月7日。関西が12月13日~1月15日です。
・避けるべき期間
門松は正月事始めといわれる12月13日以降であればいつ飾っても良いとされていますが、次の日に飾り始めるのは縁起が悪いため避けるのがおすすめです。
・12月29日:二十苦、苦松=苦が待つ、を連想する
・12月31日:一夜飾り、一日飾りで神様をおろそかにする
現代はクリスマスが終わってから飾る家が多くなっています。年末が近くなってから飾るのであれば、12月28日がおすすめ。末広がりという意味合いから、縁起が良いとされていますよ。
■門松を飾る場所はどこ?マンションなどの集合住宅の場合は
ここでは、住まいの種類別に門松の飾り方をご紹介していきましょう。
・【一軒家】門前や玄関先に飾るのが一般的!

一軒家の場合は、門の前や玄関を出たドアの前に飾るのがスタンダード。門松は「雄松」と「雌松」の対になっていて、正面から見た際に左側に松、右側に雌松となるように置きます。これは「出飾り」と呼ばれる飾り方で、門松の竹のうち2番目に長い竹が外側になるのが目印です。
・【マンション、アパート】集合住宅では松飾りでOK

多くの世帯が住むマンションやアパートなどでは、小さめの門松を室内に飾ってもOK。玄関の飾りスペースや床の間などに置いても大丈夫ですよ。
門松を飾るのが難しい場合は、玄関ドアに吊る「松飾り」を用意するのがおすすめです。松飾りであればお正月前に100均やスーパーなどでも多く販売されているので、どこで買うか悩むこともありません。松飾りはドアの外側に吊るすのが難しい場合は、内側でも構いません。
■松の内最終日には門松を仕舞おう!処分方法は
松の内の最終日には、門松も含めてお正月飾りを仕舞いましょう。立派なお正月飾りは来年も使いまわしたいと思うかもしれませんが、毎年新調するのが本来の飾り方です。
門松や他のお正月飾りは、次のような方法で処分しましょう。
・地域のどんどの日をチェック!どんど焼きに持っていく

「どんど焼き」とは1月中旬に神社やお寺、自治体ごとに行われる火祭りのことです。関東での呼び方は「どんど焼き」が一般的ですが、関西では「とんど焼き」、東北では「どんと焼き」が主流。長野県や山梨県などの甲信越では「道祖神祭」など、呼び方は地域によってさまざまです。
どの地域でもお正月飾りはどんど焼きでのお焚き上げが基本。地域により日にちは異なるため、どんどの開催の有無や日程はあらかじめ確認しましょう。
・どんどがなくてもOK!神社やお寺に持っていく

どんど焼きがない場合や日程が合わない場合は、神社やお寺に持参すれば問題ありません。多くの神社、お寺ではお正月飾りを無料で焚き上げて処分してくれます。
・お焚き上げができない場合はゴミとして処分

縁起物を一般ゴミとして出すことに抵抗があっても、適切な手順を踏めば大丈夫です。感謝の気持ちを持って塩で清め、自治体のゴミ分別ルールに従って門松を分解して処分しましょう。
■門松の由来や飾り方をきちんと知って気持ちよくお正月を迎えよう
なんとなく飾っている門松にも、古い歴史や意味合いがあるんですね。せっかく飾るのであれば正しい飾り方で飾って年神様をお迎えし、気持ちの良い新年を迎えてくださいね。
あわせて読みたい

Lifestyle
2025.12.27
正月飾りはいつからいつまで飾るのが正解?お正月飾りの意味や正しいルール、処分方法まで
mamagirl WEB編集部
Recommend
[ おすすめ記事 ]

Lifestyle
「余ったお餅も秒でなくなる!」絶品リメイクレシピ♡材料2つで簡単にできるサクもちドーナツの作り方 rin

Lifestyle
「無印良品でおうち時間がもっと好きになる♡」人気YouTuber厳選のおすすめアイテム全17選|第1弾 sena

Lifestyle
「むしろ効率がいいんです」2本を使い分けて脱・ストレス!計算尽くしの神トングをゲットせよ【大人の家庭科⑨】 藤原奈津子

Lifestyle
「参上!我ら紅葉仮面!」自然のお面がかわいすぎるワンコたち♡ mamagirlWEB編集部

Lifestyle
【コスパのいいお菓子】小分けできる個包装のおすすめ16選!手土産やバレンタインのギフトにも ユーコ

Lifestyle
まるで旅した気分♡セブンが仕掛ける【イタリアンカフェ】が本格的! 森由紀子
Check it out!