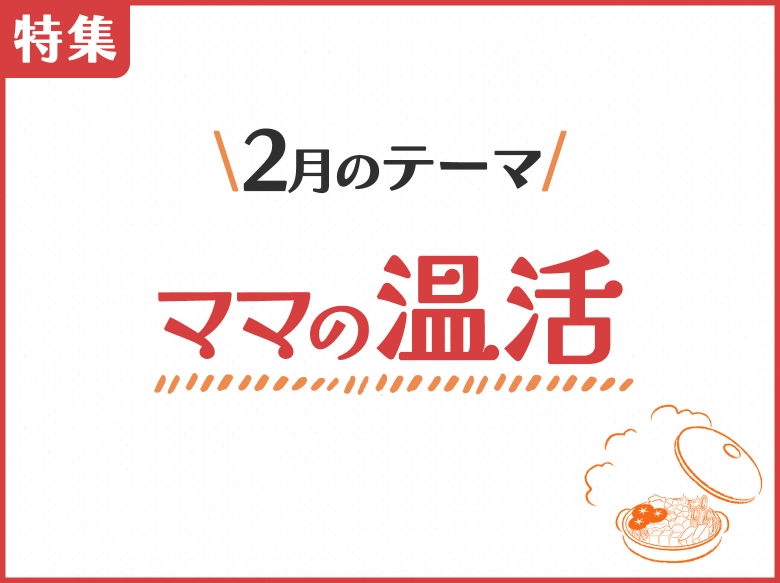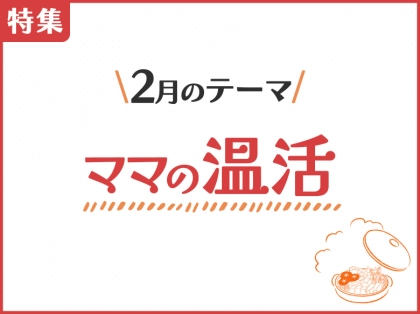出典:photoAC
Lifestyle
お正月飾りはいつまでに飾るのが正解?自分で作る方法も紹介☆
お正月飾りについて深く知れば、お正月の準備もますます楽しくなるはず☆さっそく詳しく見てみましょう!
■飾る意味や時期は?知っておきたいお正月飾りの基本

お正月飾りを飾る意味や時期などについては、実はあまりわからない人も少なくないはず。そこでまずは、お正月飾りの基本をご説明します。
・お正月飾りにはどんな意味があるの?
日本のお正月は、ただ新しい年を祝うだけではなく、豊穣の神様である“歳神様”をお迎えするのが目的。そのためお正月飾りにも、ただの飾りつけではなく、歳神様を迎えるためという大切な意味があります。
・お正月飾りを飾る正しい時期はいつ?
12月13日から1月7日までは“松の内”と呼ばれ、お正月飾りを飾るのは、この松の内の期間にあたる12月13日以降が良いとされています。ただし29日は“二重苦”を連想することから縁起が悪く、31日だと“一夜飾り”といって神様に失礼とされるので、遅くとも28日までには飾るのがオススメです。
・お正月飾りはいつ片づけるのが正解?
お正月飾りは、松の内が終わる1月7日まで飾るのが一般的。ただし関西地方など、地域によっては1月15日まで飾るケースもあります。ちなみに鏡餅を片づける鏡開きは、1月11日に行う地域が多いようです。
・使い終わったお正月飾りの正しい処分方法は?
もう使わないとはいえ、お正月飾りは神様のために飾っていた神聖なもの。ほかのゴミといっしょにそのままポイ!は避けたいところです。毎年1月15日には、各地の神社などで“どんど焼き(どんと焼き、左義長)”と呼ばれるお焚き上げ行事が行われるので、お正月飾りはそこで処分します。もしも近くでどんど焼きがない場合などは、正月飾りを新聞紙などのうえに置き、塩でお清めをしてから紙に包んでゴミに出しましょう。
■お正月飾りの種類やそれぞれを飾る意味は?
続いては代表的なお正月飾りの種類を、それぞれの持つ意味とあわせてご紹介します。
・門松は歳神様をお招きするための目印

家の門の前に飾る“門松”は、歳神様をお招きするための大切な目印。竹や松で作られたものを飾るのが一般的ですが、最近では住宅事情などから門松は飾らない家庭も少なくありません。その場合は、玄関先に小さい門松や門松のイラストなどを飾ります。100均などで販売されている、ミニサイズの門松などでも良いでしょう。
・しめ縄は家の中に厄を入れないための結界

家の玄関のうえに飾る“しめ縄”は、穢れや厄といった良くないものが家の中に入らないようにする結界としての意味を持ちます。ちなみに“しめ縄”は単純にわらで作られた縄のことで、これにゆずり葉やウラジロ、ダイダイ、シデといった縁起物の植物を飾りつけたものが“しめ飾り”です。
・鏡餅は家にやってきた歳神様が宿る場所

お餅を重ねて床の間などに飾る“鏡餅”は、歳神様へのお供えものであるだけではなく、歳神様が宿るための場所としての意味も持ちます。古くから、鏡は神様が宿るご神体とされてきました。そのため形は青銅鏡に似せて丸く作られ、名前も“鏡餅”とつけられたのです。
・羽子板は女の子の成長を願う厄除けの飾り

羽根つきに使う“羽子板”は、もともとは病気を運ぶ蚊が寄りつかないように、という厄除けの意味を持つ飾り。子ども、特に女の子が病気せず元気に成長するように、といった願いが込められたもので、花飾りなどをあしらった羽子板の置物なども販売されています。
・破魔矢は厄除けの意味を込めた神具

初詣などで入手することも多い“破魔矢”は、名前の通り“魔を破る”ことを意味し、厄除けや魔除けの願いが込められた神具です。なお破魔矢は男の子の厄除けと成長を祈る場合にも用いられ、男の子の初節句や初正月に贈られる風習などもあります。
Recommend
[ おすすめ記事 ]

Lifestyle
TikTokをアプリなしで見る方法【画像つき】ウェブ(ブラウザ)版や検索方法も解説! さんちゃん

Lifestyle
「花粉症の症状を和らげる食べ物は?」花粉症に効くおすすめの食事解説 ユーコ

Lifestyle
「冷え性ママ必見」「あたたかグッズで温活!」【KEYUCA】の売れ筋アイテムは?! mamagirl WEB編集部

Lifestyle
「今の季節しか食べられない!」いちご好きが歓喜する【ガスト・ロイホ・デニーズ】ファミレス限定パフェ3選 りえまる

Lifestyle
100均・ダイソーのおすすめティッシュケース!おしゃれな人気アイテムと売り場情報も はらわ

Lifestyle
【イタリアから直送!】コストコのティラミスカップの値段やカロリーは?おしゃれ容器の再利用法も マコ
Check it out!