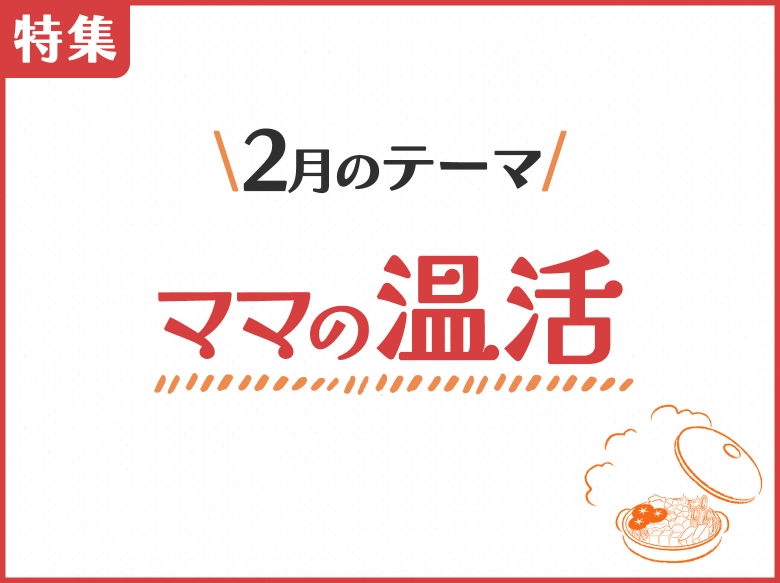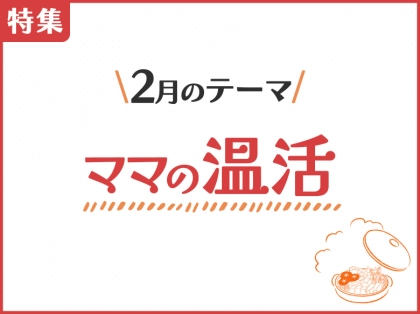Lifestyle
良い睡眠ってどんな状態? 睡眠中に体内で起きていること【ママのための睡眠講座1】
子どもの寝かしつけや、自分自身の睡眠に悩みを抱えているママは多いはず。そこで、睡眠や入浴、運動の研究をしている日本薬科大学の石川泰弘先生にインタビューを実施しました。睡眠でしっかりと体を回復させる方法や上手に眠るためのルーティンなど、眠りにまつわるアレコレをたっぷりお聞きする全3回の連載です。第1回は、睡眠の基礎知識についてご紹介。
日本薬科大学 スポーツ薬学コース特任教授 博士。2006年より㈱バスクリンの商品及び企業PR・IR活動を行い「きき湯シリーズ」を大ヒット商品に。 「お風呂博士」として TV・雑誌・Web・ラジオなど多くのメディアで活躍。 ラグビー日本代表チームをはじめ多くの日本代表チームやトップアスリートに対して入浴や睡眠を活用したリカバリーに関する講演を行う。 2022年4月より文部科学大臣認定 職業実践力育成プログラム漢方アロマコース運営委員長に就任。
「よく寝た!」と思えたら、良い睡眠ができた証拠
―そもそも親子で目指すべき「質が高い睡眠」とは、どんな睡眠なのでしょうか?
石川先生:実は、何をもって「質が高い」と定義するかは、個人差が大きいので、非常に難しいのです。そこで私自身は、「質が高い睡眠」の判断基準を、目が覚めた時に疲労感が残っておらず、日中眠くならないこととしています。
もちろん、睡眠時間や深さを測定し、分析することはできます。しかし、メンタルの状態や気分によって、睡眠に対してどう感じるかは変わるものです。たとえ8時間以上眠っていても「眠れていない」と感じる方もいますし。「よく寝た!」と思えたら、それは自分にとって質が高い睡眠だったと言って良いのではないでしょうか。
―眠りの深さや寝付きやすさにも個人差があると思います。これは生まれつきの体質が関係するのでしょうか?
石川先生:体質と生活習慣などの後天的なものの両方の影響を受けます。昼に起きて夜に眠るという1日のリズムにはたしかに遺伝子レベルでの個人差があります。ただ、やはり生活習慣の影響もかなり大きい。
よく「私はショートスリーパー体質だから睡眠時間が短くても問題無い」という人もいますが、それは本当に稀なこと。ちなみに僕は本当のショートスリーパーに出会ったことがありません(笑)。
どれだけ寝ても、14時頃に眠くなる不思議
―必要な睡眠時間も生活習慣によって変わるのでしょうか?
石川先生:そうですね。結局のところ個人差が大きいです。例えば7時間睡眠ですごく調子が良い方もいれば、8時間は必要だという方、6時間でもそこそこ元気だという方もいますよね。これは遺伝的な要因もありますが、24時間の生活習慣が大きく影響していると思います。
―たしかに、日中体を思いっきり使う人と、座って過ごす人とでは体の疲れも違いますし、必要な睡眠時間も変わりますよね。
石川先生:ただし、体をあまり動かしていないからといって睡眠時間が短くて良いというわけではありません。人が消費するエネルギーのうち20%は脳が使っています。だから、デスクワークの方も、しっかり睡眠をとる必要があるんですよ。

―夜にどれだけよく寝ても、日中眠くなってしまう気がするのですが…。
石川先生:眠くなるのは14時頃ですよね? それは体のリズムとして仕方がないことなんですよ。眠気に大きく関係するのが、体温のリズムと眠気のリズム。14時頃は食後の血糖値の上昇が影響する人もいるでしょう。リズムとして眠くなると理解しておくと良いでしょう。
1日の始まりから考えると、体温が一番低いのは朝4時〜5時。この時間帯は血圧の変動が激しいので、急に動くことは控えた方が良いですよ。この時間帯に起きてすぐ犬の散歩などに出かける方がいますが、本来はお茶でも飲んで体を起こしてから動き出さないとダメ。
そして時間の経過とともに体温が上がり、夕方6時〜夜8時頃に一番高くなります。だからこの時間帯に運動をすると良い結果が出やすい。その後、体温が下がって眠くなる。体温と眠気のリズムはこのようになっています。
ちなみに、眠くなる14時頃に「事故を起こさないように」と始まったのが、おやつの習慣。八つ時(2時)に取るから「おやつ」なんです。眠くなった時にひと息ついてからまた動き出しましょうという意味があります。おやつを3時と思ってしまうのはTVCMの影響ですね。
記憶を定着させ、体も成長する睡眠とは
ー眠っている間、人間の体内ではどのようなことが起きているのでしょうか?
石川先生:まず睡眠中の脳の動きから。睡眠中は、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」を繰り返しています。レム睡眠とは、寝ている間に脳が動いている時間。眠っていても眼球はチラチラ動いているんです。逆にノンレム睡眠は、脳もあまり動かず、眼球は動いていない、いわゆる深い睡眠のこと。

石川先生:人は眠り始めに、まず深い眠り=ノンレム睡眠状態になります。この時、脳内では記憶の選別を行っているんです。「この記憶は要る」「これは要らない」というように選別をしています。その後のレム睡眠で、脳は動きながら「その記憶をいつ引っ張り出せば良いか」という、記憶のインデックスつけ作業を行っています。記憶の定着はレム睡眠とノンレム睡眠の両方が関与しているので、ある程度睡眠時間を取らないと、記憶を定着させ、必要な時に思い出すことができないんですよ。
ー「一夜漬け」をしてもすぐに忘れてしまうのはこのせいなんですね…。
石川先生:まさにその通り。しかも、よく寝ている方の方が、記憶や学習と強くかかわる脳内の「海馬」の体積が大きいことが研究で分かっています。最近では大学受験の予備校でも「受験生でも1日7時間は寝なさい」と言われているそうです。それほど、睡眠と記憶の定着には深い関係があるということ。
一方、体の方は、最初の深い眠り=ノンレム睡眠の時に成長ホルモンが多く分泌されています。成長ホルモンは、骨を伸ばしたり体を大きくしたりするホルモン。栄養を吸収し細胞の修復にも大きく関与しているので、大人にとっても重要なんですよ。特に大人は成長ホルモンの分泌量が成長期の子どもに比べて少ないので、意識してしっかり睡眠をとらなければなりません。つまり、体にとっては、成長ホルモンを出すために最初にいかに深い眠りにつくかが大切。だから入眠時の環境を整える必要があるんです。
ー夢を見る時と見ない時があるのはなぜなのでしょうか?
石川先生:実は、夢は毎日見ているんです。多くはレム睡眠の時に夢を見ていて、その内容を覚えているのはレム睡眠中に目が覚めたということ。ちなみに、夢に出てきた景色は、必ずどこかで見たことあるものなんですよ。例えば映画のワンシーンなど、意識として残っていなくても、脳内では覚えているんです。

奥深い睡眠に関するメカニズム。第2回では、子どもの睡眠と大人の睡眠の違いを解説いただきます。
【石川先生も講師を務める、日本薬科大学の漢方アロマコース2025が開講】
健康に関わる様々なプロが直接指導するアロマの本格講座です。e-ラーニングやスポットでの受講も可能♪ 詳しくはこちら→ https://www.nichiyaku.ac.jp/kampo-aroma-course/
あわせて読みたい

Lifestyle
2025.03.10
子どもは何時間寝るべき? 眠れない夜に寝る方法【ママのための睡眠講座2】
菱山恵巳子
1991年生まれのライター・コラムニスト。エンタメからビジネスまで、執筆ジャンルは多岐に渡る。恋愛漫画の原作も手掛ける。2016年に出産、男女の双子を育てる母。男性アイドルウォッチャー。
https://www.instagram.com/emiko_hishiyama/
Recommend
[ おすすめ記事 ]

Lifestyle
「気持ち良さすぎ~」なモフモフ寝姿に思わず歓喜♪ mamagirl WEB編集部

Lifestyle
「無印良品でおうち時間がもっと好きになる♡」人気YouTuber厳選のおすすめアイテム全17選|第1弾 sena

Lifestyle
まるで旅した気分♡セブンが仕掛ける【イタリアンカフェ】が本格的! 森由紀子

Lifestyle
【子連れカフェ】これがあれば無敵☆授乳室・おむつ台・キッズスペースがあるカフェ『UPCOFFEE』(埼玉県) peggy

Lifestyle
「やっぱり鍋料理がいいね!」「芯からあったまる~」今こそ出番!【ピェンロー】でオレンジ白菜の甘さを堪能♡ hiroko

Lifestyle
「余ったお餅も秒でなくなる!」絶品リメイクレシピ♡材料2つで簡単にできるサクもちドーナツの作り方 rin
Check it out!